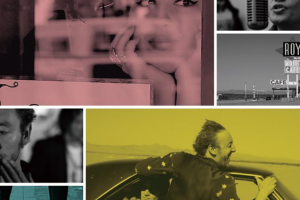重く美しい物語
チリの砂漠を舞台に描かれる神や信仰をテーマにした物語です。
チリの北部の小さな村や集落の風景を通して、救いというもののあり方を紐解き直したような美しい作品です。
重厚な事柄をテーマにしながらも、どこまでも美し映像でその風景は奏でられていきます。
あらすじ
幼い頃、神の言葉を目の当たりにした男。事故で足に大けがを負った友人のために奇跡を起こそうと、チリの砂漠を旅し続け、人里離れた友人宅に到着するが…。
引用:Netflix
キャスト・スタッフ紹介
- 制作国:チリ・フランス合作
- 公開年:2016年
- 上映時間:85分
- 監督:クリストファー・マーレイ
- 出演:ミカエル・シルバ、バスティアン・イノストロサ、アナ・マリア・エンリケス
予告編
荒野の風景の中で
チリの北部の砂漠というあまり我々にとって馴染みのない土地が舞台となっています。
タマルガル・パンパというりい北部の村周辺を舞台に、主人公以外はその集落に住む人々をキャストに迎え入れるという試みがなされています。
そういったドキュメンタリータッチの質感がありながらも、美しい構図を保ったカットや、映像に説得力を増す長回しなど、丁寧で作り込まれた美的感覚も随所に感じることができます。
それはまるで地の果てともいうべき乾いた大地が続く環境における営みを、傍観するわけでもなく、かと言って必要以上に手助けをするわけでもない、俯瞰の必要性ともいうべき視点が垣間見れます。
絶対的に完全なるものがあるのならば、それはきっと不確実性の宝庫と化すのではないでしょうか。それは完璧が語ることは時に事実ではない物事をはらんでいるからです。
これ以上にないという隙のなさは、そこからの発展性を持たないいわばそこで完結してしまったものです。そういった物事に残されたことはもはや壊れるや崩壊といった、破壊がもたらす営みしか残されていないのです。
結局それは完璧ではなかったという事実を残す事となり、神話に普遍性を求める人々の渇望からは程遠いものと言えるでしょう。
この荒野を舞台にした物語で描かれるのはまさにこういった”もうこれ以上ないほど完璧”と思われている神や信仰、そしてそれらを崇める崇拝という行為を解体して、もう一度見つめ直そうとするそのような試みに感じられます。
崇拝するということ
何かを崇拝するということはその物事を強く信じるという行為に他なりません。
その信じるという行為は何も信仰におけるメソッドというわけではなく、人々の生活や身近な人々とのコミュニケーションにも当然ながら有効です。
そしてそれがあるからこそ我々人間は”当然”や”完成”といった”出来上がった形”をそこに見いだすことが出来るのではないでしょうか。
それは人間が生み出した”数字”や、枝分かれしつつもそれぞれにおいて確固たる立ち位置を確立する”言葉”というものに反映され、人々の関係性や生活の秩序を生み出していると言えるでしょう。
“はじめに言葉ありき”という一節は新約聖書のヨハネによる福音書の有名な一節ですが、まず最初に言葉があるという状況は考えてみればおかしなことです。人間がいなければ言葉は生まれないと誰もが思うはずです。
しかし言葉には概念というものがつきまといます。この概念というものは人間が存在しなくても存在することが出来るのではないかと考えることも出来ます。
つまり人間が作ったと思える思想や考え方ははじめからそこにあって、それをなぞっているに過ぎないという取り方も出来るのではないかと思うのです。
冷たいものを冷たく感じたり、温かいものを温かく感じるという行為は、人間が存在するからこそそこにあるのか、その概念こそ先にあるからなのか、こういったことを議論すると卵が先か鶏が先かといった禅問答めいた議論に発展してしまいそうです。
しかしその現象は初めからそこにあるのであって、人間が作り出したものではありません。それを温かいか冷たいか受け取るのは、進化がもたらした結果であって、当初の事実は人間が出来上がる前からそこに存在したのではないでしょうか。
そういった想念のようなものを形にしたものが”言葉”であるならば、まず最初に言葉があったという言い分も理解できなくもありません。
そしてその言葉を実態化するいくつかの方法論として信仰や崇拝が生まれたという見方をここではしておきます。
信仰の再構築
信仰や崇拝は何かを信じることを強く渇望する我々人類にとって、時にはなくてはならないものであったりします。
“これはこうである”や”これがあったからこうであった”という秩序に基づいた考え方を人々は愛します。信じるという行為の裏側にはまさにこの取り決めが鎮座していて、”信じるものは救われる”といった考え方に結びつきます。
なんだかんだ言って人々は理由が大好きです。あらゆる領域において理由のない出来事なんで外道扱いされて当然であると言った、暗黙の了解を感じることも少なくありません。
しかし信じていれば救いがもたらされると言った、傍観されることを受け入れる考え方は、当然ながら犠牲をはらんでいるかのように映ることもあります。
この映画の中で描かれる小さな村でギリギリの生活を強いられる人々は、まさにこの救いをどこまでも信じていて、信仰することや崇拝することになんの疑問も抱いていないように感じられます。
そして主人公の青年マイケルは、その信じ続け祈り続ける状況に異議を申し立てるように、新たな救済をそこに提示していきます。
人々はそこに怪しさや異端を当然のことながら感じるのですが、よくよくマイケルの言うことに耳を傾けると、それは新しい何かをそこに創造しようとしているのではなく、信仰や崇拝をもう一度見直して再構築するという作業をしようとしているだけなのではと思えます。
マイケルは「神は外側にいるのではなく、内在するものである」と語ります。それは人々それぞれが救いのあり方を見つめ直そうと言うメッセージに感じられます。
そしてそれこそが奇跡を起こす手段であると言うことが出来るのではないでしょうか。つまり驚きや輝きを作り出すのは結局のところ自分自身でしかないのです。
それこそがこのどこまでも達観され傍観されたような、神に見放されたと感じる世界での生きる術なのではないでしょうか。
![fylmu [フィルム]|いつでも映画の話をしよう。](https://fylmu.com/wp-content/uploads/2017/07/logo.png)